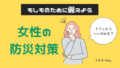こんにちは。
今月も6まる-blogでは防災対策についての記事をお届けします。
夏休み、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
8月は台風や集中豪雨が増える時期であり、9月の「防災の日」に向けても意識が高まる季節。
この機会にぜひ親子で「防災対策」を楽しく学んでみませんか?
今回は、夏休みにぴったりな親子でできる防災体験5選をご紹介します。

おうちで防災宝探し!
夏休みはお子さんと一緒に楽しみながら防災知識を身につける絶好のチャンスです。
今日からさっそく始められるのが「おうちで防災宝探しゲーム!」リビングや子供部屋、玄関など、家の中に隠されている防災グッズを親子で力を合わせて探してみましょう。
- 懐中電灯はどこ?
- 非常食は何がある?
- 飲み水はどれくらい?
- 電池やモバイルバッテリーは?
クイズ方式で出題して遊び感覚で探すことで、いざという時に「あれ、どこに置いたっけ?」とならずに済みます。さらに、見つけたグッズの使い方や有効期限を確認することで、防災意識が自然と高まります。
何もない平和な日だからこそ、ゲームのように楽しみながら備えておくことが大切です。
小さなお子さんでも、自分で見つけた“防災グッズ”にはきっと愛着がわくはず!
「防災って、意外と面白いかも!」
そんな気持ちになれたら、大成功ですね。
非常持ち出し袋を一緒に準備!
子ども用の持ち出し袋も用意してみよう。
大人用の非常持ち出し袋を用意しているご家庭は多いかもしれませんが、
子ども用の防災バッグは意外と盲点になりがちです。
避難時は、大人も手がふさがる場面が多く、子ども自身が必要なものを持っていることが大きな安心感になります。
子ども用バックに入れておくと安心なもの
- 飲みきりサイズの水
- マスク・除菌シート・ばんそうこう
- すぐに食べられるおやつ(ゼリー、ビスケットなど)
- ミニタオル・着替え(下着や靴下も)
- 小さなおもちゃやぬいぐるみ(心を落ち着かせる“安心アイテム”)
- 保護者の名前・連絡先・避難先を書いたカード
- 写真(家族の顔やペット)
自分で選んで詰めることで、いざという時の安心感につながります。「ぬいぐるみはかさばるけど、どうしてもこれだけは入れたい!」そんな子どもの声にも耳を傾けながら準備すると、「自分だけの“お守りリュック」になります。
年齢に応じて中身を見直すことも大切!
成長とともに必要な物は変わってきます。
新学期や春・夏休みなどの節目に「防災リュック見直しタイム」を設けるのもおすすめです。「子どもだからできない」ではなく、
「子どもだからこそ、備えてあげたい」「子ども自身に少しでも任せたい」
そんな気持ちで、楽しく一緒に準備してみましょう。
地図を使って“避難ルート探検”!
身近な道にこそヒントがいっぱい!親子で安全ルートを確認しよう。
災害が起きたとき、どこに避難するか・どうやって向かうかをあらかじめ知っておくことは、とても大切な防災行動のひとつです。
特に子どもにとっては、「避難」という言葉が抽象的でイメージしにくいことも。
だからこそ、実際に“歩いて体験すること”が学びへの近道!
親子で探検気分を味わいながら、自宅から避難所までのルートを歩いてみましょう。
スタートは地図から!チェックリスト
- 一番近い避難所はどこ?(小学校や公民館など)
- 避難所までの道のりに危ない場所はない?
- 他にも予備ルートはある?(川沿いや狭い道は避ける)
「ここを通ると公園があるよ」「あっちの道は信号が少ないね」など、地図を読みながら子どもと一緒にルートを選ぶプロセス自体が防災教育になります。
歩きながら防災について話すことで、「なぜ避難が大事なのか」を理解するきっかけになります。
実際に歩いてみよう!“プチ防災探検”のすすめ
時間帯は昼間でも夕方でもOK。
歩きながらこんなポイントを一緒に観察してみてください。
危険ポイントの発見
- 倒れそうなブロック塀はない?
- 電柱・看板・ガラス張りの建物など、地震時に危険なものは?
- 大雨のときに水が溜まりやすい低い場所や側溝はある?
安心ポイントの確認
- 街頭が多くて明るい道は?
- 人通りのある道、交番、商店は?
- 公衆電話や非常ベルがある場所は?
子どもの“体感”を大事に
- 「この道はちょっと暗くてこわいな…」
- 「ここを走っていったらどれくらいかかる?」
そんな感覚もとても重要です。
“実際にやってみる”ことで自信につながる
避難訓練とは違い、「自分の家から、自分の足で歩く」体験はリアリティがあります。
「いざという時、ここを通って避難するんだ」と理解することで、子どもにも「自分で動ける力」が育ちます。
楽しみながら備える、夏の“防災遠足”に!
- なるべく日中と夕方、異なる時間帯で歩くのが理想
- 荷物を背負った状態で歩いてみると、実際の避難を想定しやすい
- 一度歩いたら「終わり」ではなく、季節や天候によって再確認も◎
探検感覚で歩いて、地図に書き込んで、おうちに帰ったらふりかえり。
ちょっとした防災×冒険気分の夏の思い出になります。
「防災=お勉強」ではなく、
「防災=探検・発見・挑戦」に変えてみましょう!
“水なしごはん”を作ってみよう!
非常食を実際に体験してみる
「非常食って本当においしいの?」「どんなふうに食べるの?」
──そんな疑問を解消するには、実際に食べてみるのが一番!
防災訓練というと堅苦しい印象もありますが、非常食の試食は**おうちで気軽にできる“おいしい防災体験”です。
親子で「水や火が使えない状況」を想定しながら、防災ごはんにチャレンジしてみましょう!
アルファ米や缶詰、レトルト食品などを使って、水や火を使わずにできる防災ごはんを親子で作ってみましょう。
おすすめメニュー
・アルファ米に水を注いで食べる
・缶詰のパンやスープを温めずに試食
・ポリ袋クッキングに挑戦!
「これ意外とおいしい!」「これだけじゃ足りないね」など、実際に体験することで学びも深まります。
体験から生まれる“気づき”が学びに!
・「これ1食分にしては少ないかも?」
・「スプーンがないと食べにくいね」
・「アルファ米って、戻す水の量けっこう使うね」
──こうした“リアルな感想”を家族で話し合うことで、
非常時に必要な備えの具体性がぐっと高まります。
子どもも楽しめるアイデア
- 非常食を使って“ミニ防災レストラン”ごっこ
- 「☆印レビューシート」をつくって、味・満腹感・食べやすさを星で評価
- 写真を撮って、自由研究やSNSにも活用!
非常食の備蓄は“回して食べる”が基本!
体験後に賞味期限の近い非常食は、日常で美味しくいただいて、また買い足す“ローリングストック”で備えましょう。
「おいしい!」も、「もう少し工夫したいな…」も、
すべてが実践的な防災の学びに変わります。
「食べる」という一番身近な行動だからこそ、
子どもたちにとっても記憶に残る体験になりますよ♪
“停電ごっこ”でサバイバル体験!
もし今、電気が使えなくなったら?をおうちで体験しよう
災害時によく起こるのが停電。
夜に突然明かりが消えたら…テレビも見られない、冷蔵庫も止まる、スマホも充電できない──そんな状況を、**実際におうちで体験してみる「停電ごっこ」**がおすすめです!
子どもにとってはちょっとワクワク、大人にとっては備えの確認ができる、楽しく学べる防災シミュレーションです。
やり方は簡単!“○○時間だけ停電生活”
やってみる時間の目安
- 平日の夜1〜2時間
- もしくは、休日の夕方から寝る前まで
実際にやること
- 家の主電源 or ブレーカーを落とす(or部屋ごとの電気を消す)
- 冷蔵庫やWi-FiはそのままでもOK(初回は“プチ停電”でも)
- 電気を使わずに、懐中電灯やランタンで過ごしてみる
チェックしておきたいポイント
- 懐中電灯はすぐに取り出せた?
- モバイルバッテリーの残量・保管場所は?
- ラジオは電池式?使い方はわかる?
- トイレや手洗い場まで安全に移動できた?
子どもにも、「このライト、どうやってつけるの?」「階段こわい…」などリアルな体験を通じて、**“停電=不便”だけど、“備えがあれば怖くない”**という感覚が育ちます。
より楽しくするアイデア
- 懐中電灯をテーブルの下から照らして“影あそび”
- コップにライトを入れて“即席ランプ”を作る
- 停電中に食べられる非常食で“夜の防災ディナー”
- 親子で「防災クイズ大会」
- ランタンの明かりで絵本タイムや昔話をしてみる
電気がなくても過ごせる工夫=防災力アップ!
親子で“自分で何とかする力”を育てる
電気がなければ何ができない?
じゃあどうやって過ごす?
家族で話し合いながら過ごす数時間が、きっと子どもの心に残ります。
「備えるってカッコいい」「自分でできることがある」
そんな実感が、未来の防災力につながっていきます。
“停電ごっこ”は、暗闇で困ることをリアルに体験できる貴重な時間です。
ゲーム感覚で楽しみながら、災害時の暮らしを少しだけ味わってみることが、最も実践的な防災教育になりますよ!
まとめ:この夏、防災を“楽しく学ぶ家族の時間”に!
夏休みは、家族と一緒に過ごせる貴重な時間です。そんな機会を活かして、防災対策についても楽しく・前向きに取り組んでみませんか?
今回ご紹介した「親子でできる防災体験5選」は、どれも特別な準備がいらず、自宅や地域の中で実践できる内容ばかりです。「防災宝探し」や「非常持ち出し袋の準備」「避難ルートの探検」など、遊びや自由研究のように体験しながら、子どもたちが自然と防災を身につけられる工夫を盛り込みました。
「防災=怖いこと」ではなく、「家族で支え合う力」「生き抜く知恵」として、親子で共有できる時間を持つことが、いざという時の大きな備えになります。防災は一度きりのイベントではなく、日々の生活の中で少しずつ身につけていくものです。
まずは、今回の体験の中から一つ選び、気軽に始めてみてください。その一歩が、家族の安心と、子どもたちの“生きる力”につながります。
6まる-BLOGでは今後も、日常に取り入れられる防災対策のアイデアを発信していきます。次回もぜひご覧ください。