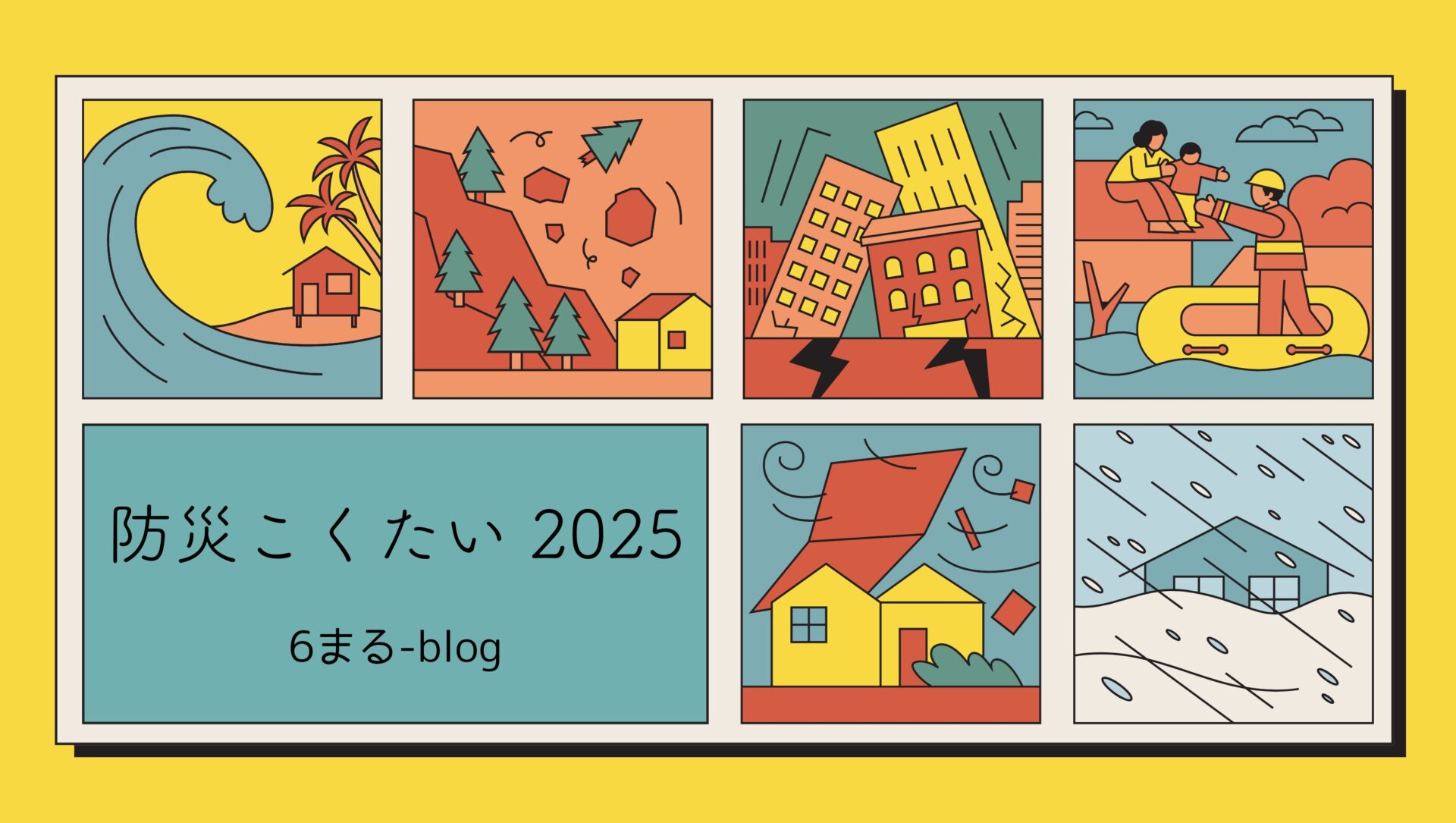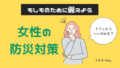今年9月、新潟で開催される「防災国体2025」。
テーマは 「語り合い・支え合い」。
地震や豪雨、台風など、自然災害が相次ぐ日本にとって、防災はもはや「自分ごと」として向き合うべき大切なテーマです。
会場では最新の防災グッズや非常食の展示、VRによる避難体験、専門家による講演など、多彩なプログラムが予定されています。子どもから大人まで楽しみながら学べる仕掛けが用意されており、防災を「知る」だけでなく「体験し、語り合う」場になっているのが特徴です。
今回は私自身も参加し、会場で感じた“最新の防災トレンド”を、写真を交えながらお伝えしたいと思います。災害への備えを見直すきっかけに、ぜひ最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

防災国体とは?
「防災国体」は、2016年から毎年開催されている 日本最大級の防災イベント です。
国体といえば「国民体育大会」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、その名の通り、防災をテーマにした“国民的な大会”として位置づけられています。
主催は内閣府や自治体をはじめ、産学官民が一堂に会し、最新の防災・減災の取り組みや技術、知恵を共有できる場です。展示や体験ブース、シンポジウムなどを通じて、誰もが参加しやすく、防災を「知識」から「行動」へとつなげることを目的としています。
2025年のテーマは、
「語り合い・支え合い ~新潟からオールジャパンで進める防災・減災~」。
これは、地域や世代を超えて「対話」すること、そして「共助の力」で災害を乗り越えることの大切さを示しています。
開催地である新潟は、2004年の中越地震という大きな被害を経験した地域です。その教訓を全国に発信できる土地としての意義が大きく、今回の開催はまさに「災害に学び、未来へつなげる」場になるといえるでしょう。
会場の見どころと最新トレンド
2日間にわたって朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)で開催される「防災国体2025」。会場では、防災を「学ぶ」だけでなく「体験し、つながる」最新の取り組みが目を引きます。ここでは、その中でも特に注目したい最新トレンドを紹介します。
1. 専門家から子どもまで――“誰でも参加できる場”が充実
会場内には、専門家向けのパネルディスカッションから、子どもが楽しめる体験型コーナーまで、多彩なプログラムが揃っています。
例えば、南海トラフ地震や防災庁の役割に関する討論会や、子ども向けにAR(拡張現実)を使った迷路体験、地震をリアルに体験できる「ザブトン教授の防災教室」が展開されます 内閣府。

2. 体験型企画が豊富!
- 会場ツアー:防災の専門家がガイドする「ぼうさいこくたい会場ツアー」で、見逃しがちな展示の魅力がすぐ分かります。
- 中越回廊・水害治水ツアーや農業水利施設を巡る防災ツアーなど、新潟ならではの地域資源と結びついたユニークな企画も実施されます 内閣府。
3. 現場で動く“産業×技術”の展示が注目
併催の「にいがた防災産業展」では、防災関連の最先端技術や製品が多数紹介されています。防災DX(デジタルトランスフォーメーション)や避難所資材、災害対応機器など、展示ホールBに76社参加のBtoB展示として全国初の試みとして開催されます 新潟県公式ウェブサイト。
また、「いつものもしもCARAVAN」は、無印良品との共催による体験型イベントです。親子で楽しみながら参加できる工夫が満載で、防災を楽しく学ぶきっかけにもなります 新潟県公式ウェブサイト新潟|万代イベント情報。

4. 地域防災の最新情報も見逃せない
新潟県防災局によるブース展示では、土砂災害対策についてのパネルや模型展示があり、土砂災害の仕組みや警戒システムをわかりやすく解説しています ぼうさいこくたい2025。また、個別避難計画やコミュニティ防災の推進を訴えるセッションも注目ポイントとして紹介されています 新潟県公式ウェブサイト。
日常に取り入れたい防災アイデア
防災国体の魅力は、最新トレンドを知るだけではなく、「自分の生活にどう活かせるか」を考えるきっかけをくれることです。ここでは、会場で学んだことをヒントに、誰でも日常に取り入れやすい防災アイデアを紹介します。
1. 備蓄は「特別なもの」より「普段の食材」を
非常食といえばアルファ米や缶詰を思い浮かべますが、最近は「ローリングストック」という方法が注目されています。普段の食品や飲料を少し多めに買い、消費しながら補充していくスタイルです。非常食を特別視せず、いつもの暮らしの中で自然に備えることができます。
2. 家具や家電の固定は“最低限の命を守る備え”
地震の際、ケガの原因の多くは家具の転倒です。L字金具や転倒防止ベルトを使って、冷蔵庫や本棚を固定するだけでリスクは大きく減少します。会場でも耐震グッズの展示があり、日常でできる工夫の重要性を改めて感じました。

3. 災害時の「連絡手段」を家族で確認
会場では通信手段の確保やSNSを活用した安否確認についての展示もありました。家族で「災害時はまずここに連絡」「避難できないときはこの場所に集まる」といったルールを決めておくだけでも安心につながります。
4. 防災を「楽しく学ぶ」工夫を
無印良品と共催の「いつものもしもCARAVAN」では、日用品を使った防災アイデアが紹介されていました。例えばラップをお皿代わりにする、ジップ袋で食品保存をするなど、身近な道具で工夫できます。子どもと一緒に試してみれば、防災教育にもなります。
ジュニア防災検定・防災検定がオンラインで受験可能に
防災国体にあわせて紹介されていたのが「ジュニア防災検定」「防災検定」です。これらは オンラインで気軽に受験できる 検定試験で、防災の基礎知識や実践力を身につけるきっかけになります。
子ども向けの「ジュニア防災検定」は、日常生活でできる備えを学べる内容で、家庭や学校での学びに役立ちます。一方、大人向けの「防災検定」は、災害の仕組みや地域の備えなど幅広く問われ、防災リーダーを目指す方にもおすすめです。
内閣府も推奨しており、「日常から備えを意識する習慣づくり」として活用されています。興味のある方は、自宅からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

参加して感じたこと
実際に「防災国体2025」に参加してみて、一番印象に残ったのは 「防災は特別なことではなく、日常の延長にある」という実感 でした。
会場に足を踏み入れると、最新の防災グッズや非常食がずらりと並び、思わず「これなら自宅でもすぐ取り入れられる」と感じるアイデアがたくさんありました。特にローリングストックの展示では、普段の買い物の延長でできる備えの大切さを再認識。非常食というより「普段のごはんを少し先の未来のために用意する」という考え方が新鮮でした。
また、VRでの地震体験は想像以上の迫力。実際に身体で揺れを感じると、家具の固定や避難経路の確認といった“基本の備え”の重要性を、頭ではなく体で理解できました。
さらに印象的だったのは、来場者同士が自然に会話を交わしていたことです。子どもが体験ブースで学んだことを親に説明していたり、初対面の方と「うちはこんな備えをしているよ」と情報交換をしたり…。まさに今回のテーマである 「語り合い・支え合い」 が、会場のあちこちで形になっていました。
防災を“学ぶ”だけではなく、“語り合い、共有し合う”ことで、自分の備えを見直すきっかけがたくさん得られた時間でした。


防災を日常に取り入れる一歩を
「防災国体2025 新潟」では、最新の防災技術やグッズを見て学ぶだけでなく、体験し、人と語り合うことで、防災をより身近に感じることができました。
特に今回のテーマ 「語り合い・支え合い」 の通り、個人の備えだけではなく、家族や地域、そして社会全体で支え合うことの大切さを実感しました。
防災は「特別なこと」ではなく、今日からできる小さな一歩の積み重ねです。
- いつもの買い物に「ローリングストック」を取り入れる
- 家具の固定や避難経路を確認する
- 家族と連絡方法を話し合っておく
これだけでも、いざというときに大きな安心につながります。
今回の参加を通して得た学びを、ブログを通じて少しでも多くの方に届け、日常の中に防災を自然に取り入れるきっかけになればと思います。
次の災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ、「今日からできること」 を一緒に始めていきましょう。