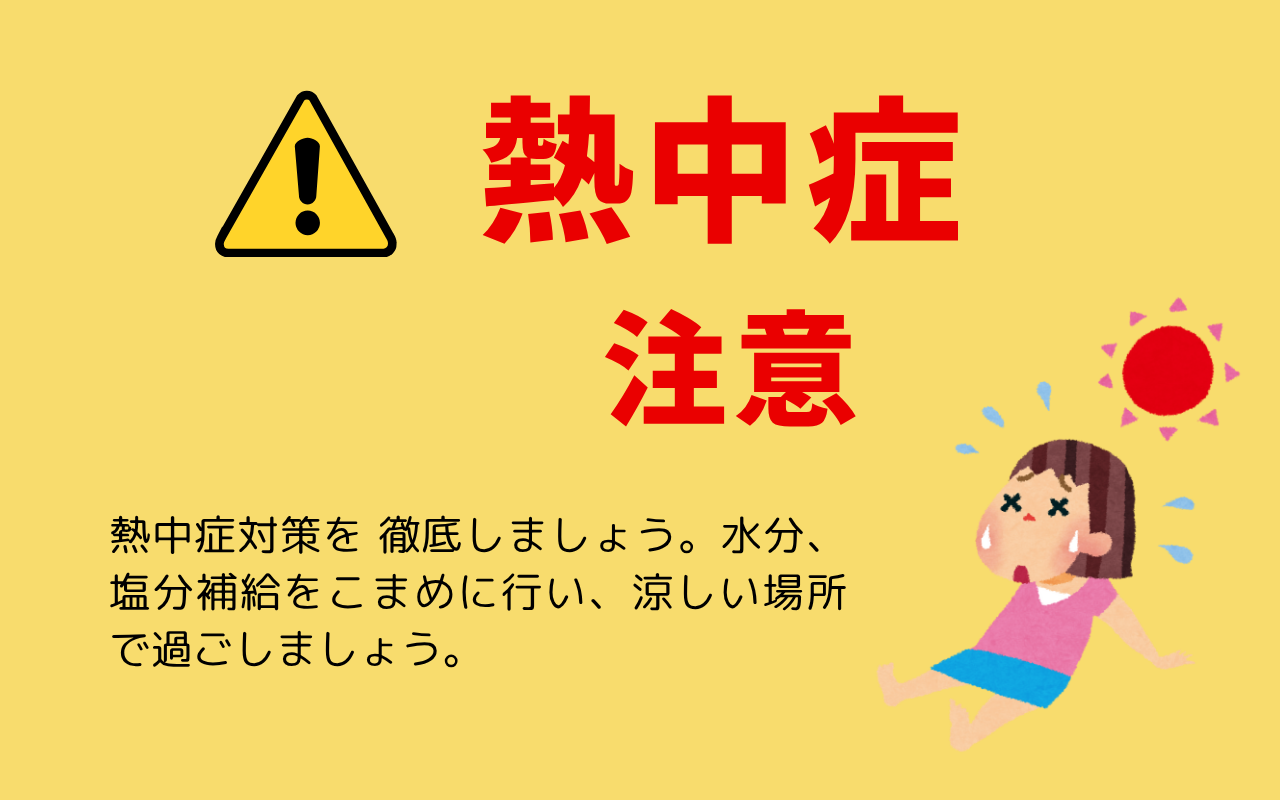気づけば汗ばむ日も増え、日差しが少しずつ強くなってくるこの季節。
まだ本格的な夏ではないから…と油断していると、実は”体が暑さに慣れていない”この時期こそ、熱中症のリスクが高まるタイミング**なのです。
特に梅雨時期は湿度が高く、汗をかいても蒸発しにくいため、体の熱がこもりやすくなります。
また、冷たい飲み物や冷房で体が冷えたり、自律神経が乱れやすくなるのもこの時期の特徴。
そんな時こそ意識したいのが、内側から整える“ナチュラル熱中症対策”。
水分やミネラルはもちろん、昔ながらの知恵や季節の食材を味方につけて、体調をやさしく整えていきましょう。
今回は、これからの季節を元気に過ごすために役立つ、自然派の熱中症対策と毎日の体調管理のコツをご紹介します。

“熱中症”なぜ早めに注意が必要なのか?
「熱中症」と聞くと真夏の猛暑日をイメージしがちですが、実は6月後半〜梅雨明け前後が最も注意が必要な時期なのです。
気温と湿度の急上昇に、体がまだ慣れていない
6月はまだ涼しい日も多く、体が「暑さモード」に切り替わっていません。
そこへ急に気温が上がると、体温調節が追いつかず、熱がこもりやすくなるのです。
また、梅雨時期は湿度が高いため、汗が蒸発しにくくなり、体の中に熱がこもりやすい状態に。
汗をかいているのに、熱が逃げずに体内にたまり、「なんとなくだるい」「頭がぼーっとする」という症状が出始めるのがこの時期です。
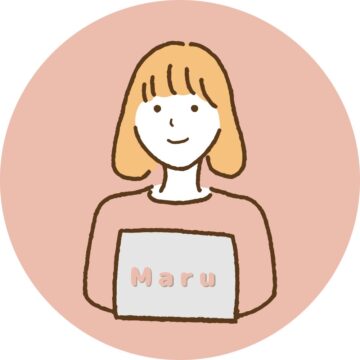
今こそ“予防がカギ”
熱中症は、かかってしまってからの対処よりも、日々の予防が何より大切です。このあとご紹介する「水分とミネラルの取り方」「ナチュラル食材の活用法」「暮らしの工夫」で、無理なく体を守っていきましょう。初夏から夏本番に向けて、体を少しずつ“暑さに強いモード”へと整えていくことが、元気に過ごすコツです。
熱中症は水分+ミネラルがカギ!
〜ただの水分補給では足りない理由〜
「水はちゃんと飲んでいるのに、なんだかだるい…」そんな時は、ミネラル不足が原因かもしれません。
汗とともに体からは、水分だけでなくナトリウム・カリウム・マグネシウムなどのミネラルも一緒に失われているのです。そこで意識したいのが、“ミネラルも補える水分補給”!
おすすめドリンク
- 梅酢+水+ハチミツ(ミネラル&クエン酸補給に◎)
- 麦茶+ひとつまみの天然塩(ノンカフェイン&ナトリウム補給)
- 甘酒+水(「飲む点滴」とも呼ばれる栄養補給ドリンク)
- 手作りフルーツビネガーの炭酸割り(クエン酸+カリウムが疲労に◎)
ポイント
- 喉が渇いたと感じる前にこまめに飲む
- 冷たすぎる飲み物は胃腸を冷やすので、常温〜少し冷たい程度がベター
- 外出時はマイボトルに入れて、携帯しやすいドリンクで補給を♪
熱中症を防ぐ「食」と「暮らし」の工夫
〜毎日のごはんと生活リズムが、体を守ってくれる〜
暑さに負けない体をつくるには、水分補給だけでなく、日々の食事や暮らしの中の小さな工夫が大切です。
食で整える
- きゅうり・スイカ・トマトなど、水分たっぷりの夏野菜で“食べる水分補給”
- 梅干し・ぬか漬け・味噌汁は塩分とミネラル補給にぴったり
- ショウガ・しそ・みょうがなど、体の巡りを良くする薬味をプラスして代謝アップ
暮らしで整える
- 朝夕の涼しい時間に軽い運動や散歩で汗をかく“暑熱順化(しょねつじゅんか)”を促す
- 首・脇・足首を冷やすスカーフや保冷グッズで体温を調節
- 室内でもこまめに除湿・換気して、熱がこもらないように工夫する
今日からできる“小さな習慣”を積み重ねて
ほんの少しの意識と、昔ながらの知恵や食材を取り入れるだけで、体はぐんとラクになります。
季節の変わり目を心地よく過ごすヒントとして、できることから取り入れてみてくださいね。
熱中症/室内でもかかります!“隠れ熱中症”とは?
「外に出てないから大丈夫」と思っていませんか?
実は、**最近増えているのが「室内で起こる熱中症」=“隠れ熱中症”**です。
外出せず冷房の効いた部屋にいるのに、なんとなく体がだるい、頭がボーッとする…。
これこそが、気づかぬうちに体に熱がこもり、脱水や体温調節のバランスが崩れている状態なんです。
なぜ室内でも熱中症になるの?
室内でも熱中症になる理由は、主に次のようなものです。
1. 湿度が高く、汗が蒸発しにくい
梅雨時期〜初夏は、外だけでなく室内も湿度が高め。
汗をかいても蒸発しづらく、体の中に熱がこもりやすくなります。
2. 暑さを自覚しにくい
高齢者は年齢とともに暑さやのどの渇きを感じにくくなるため、気づいた時には脱水が進んでいるケースも。
3. 冷房を我慢してしまう
「まだ6月だし…」とエアコンをつけずに過ごしていると、熱と湿気がこもった部屋でじわじわと熱中症に。
4. 長時間の在宅ワークや昼寝も注意
風が通らない室内で長く過ごすと、汗をかかない=水分補給を忘れがちに。
パソコンに夢中で気づいたら頭が重い…なんてことも。
“隠れ熱中症”を防ぐための小さな工夫
- 室温・湿度をチェック(温湿度計が便利!)
→ 室温28℃以下、湿度50〜60%が目安です - 除湿機能や扇風機で空気を循環させましょう
- 喉が渇いていなくても、こまめな水分補給を意識的に
- 朝起きたらまず一杯の水を。寝ている間にも水分は失われています
- 冷たい飲み物ばかりでなく、常温の麦茶やビネガードリンクなども◎
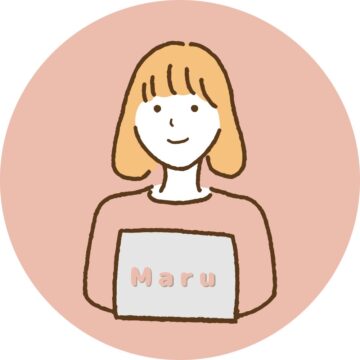
「外出しないから大丈夫」は、実は油断ポイント。
特にご高齢の方や体調を崩しやすい方は、室内でもこまめに空気を動かし、水分とミネラルを意識してとることで、“隠れ熱中症”から体を守ることができます。
これから迎える暑さに向けて、住まいの中からしっかり整えていきましょう。
熱中症/世界の暑さ対策あれこれ
世界各国では、気候や文化に合わせたユニークで実用的な熱中症(暑さ)対策が古くから行われています。ここでは、日本でも取り入れやすい視点も交えながら、いくつかの国や地域の例をご紹介します。
インド:スパイスと「ラッシー」で体を守る
インドの暑い地域では、ヨーグルトドリンク「ラッシー」を飲んで体の熱を冷まします。
スパイスもたっぷり使われますが、実はこれも発汗を促して体温を下げる知恵。
カレーなどの辛い料理は、汗をかくことで体をクールダウンさせる効果があります。
🔸ポイント:ラッシーは腸にも◎!熱中症対策+腸活にもなる飲み物です。
タイ:辛味と甘味、塩分を効率よく補給
タイの暑い気候では、スパイシーな料理とフルーツの組み合わせが定番。
スイカやマンゴーに塩や唐辛子をふって食べる習慣もあり、水分+塩分+糖分+カリウムが一度に取れる工夫です。
🔸ポイント:スイカに少しの塩をふって食べるのは、日本でも昔ながらの知恵ですね。
メキシコ:タマリンドドリンクでミネラル補給
暑さが厳しいメキシコでは、タマリンド(豆のような酸っぱい果実)を使ったジュースがよく飲まれます。
ミネラルが豊富で、電解質を補うのにぴったり。
街では塩やライムを加えてアレンジするスタイルも。
中国:苦瓜や菊花茶など“涼”を取り入れる
中国の薬膳文化では、体を「冷ます」「熱を取る」食材が知られています。
苦瓜(にがうり)、冬瓜、菊花茶、緑豆スープなどが代表格。
薬膳の考えでは、内側から“熱を冷ます”ことが熱中症対策につながります。
苦瓜や菊花茶は、中国では“体を冷やす食材”として昔から親しまれてきました。ビタミンや抗酸化成分が豊富で、夏バテ予防にもぴったり。体の中からすっきり整えてくれる、やさしい自然の知恵です。
🔸ポイント:苦瓜や菊花茶は、日本でも夏バテ防止に人気が出てきています。
フランス:日中の外出を避け、日陰を大切に
猛暑が増えてきたヨーロッパでは、午前中に用事を済ませ、日中は休息するスタイルが定着しています。
フランスやスペインでは「シエスタ(昼寝)」の文化もあり、暑い時間に無理をしないのが鉄則。
🔸ポイント:日本の高齢者にも取り入れやすいライフスタイルの工夫です。
日本の伝統的な暑さ対策
- すだれや風鈴で風通しと涼感アップ
- 梅干しや麦茶で水分・塩分補給
- 打ち水で地面の熱を冷ます
- 麻や綿の衣服で通気性を高める
🔸ポイント:自然の力を活かした暮らしの知恵が、今こそ見直されています。
熱中症/世界の知恵を、私たちの毎日に(まとめ)
世界にはその土地の気候や暮らしに合わせた、シンプルで効果的な暑さ対策がたくさんあります。
共通しているのは、「体を冷やすだけでなく、内側から整える」という考え方。
今年の夏は、そんな世界の知恵もヒントにしながら、自分らしいナチュラルな熱中症対策を取り入れてみませんか?